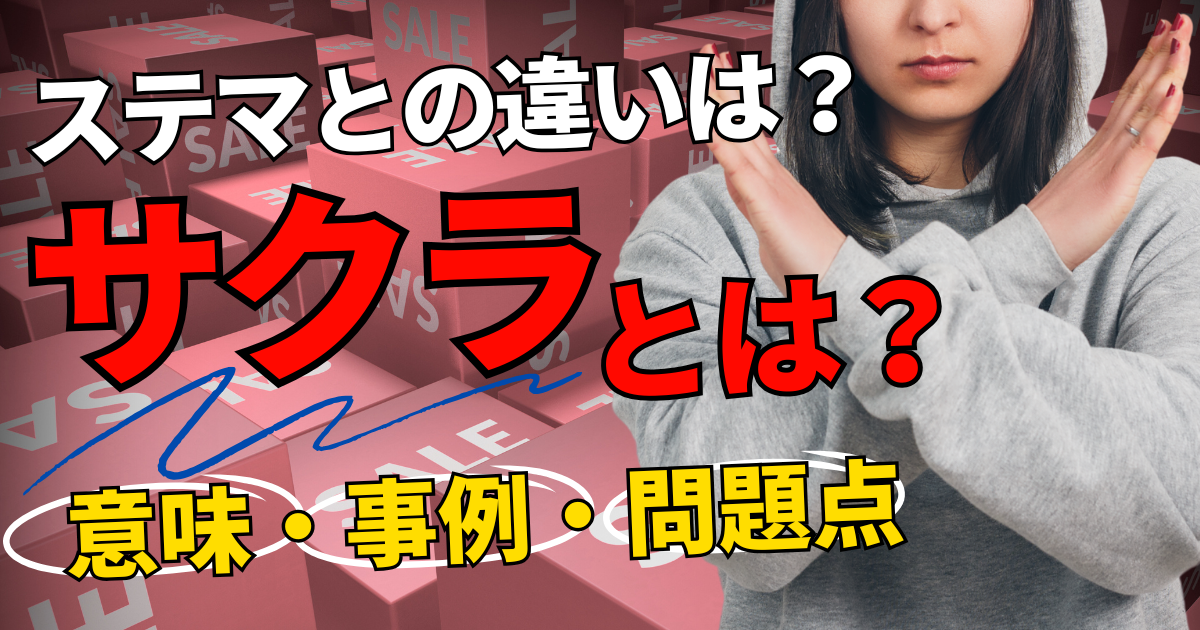インターネットやSNSの普及により、私たちは日常的に口コミやレビューを参考に商品やサービスを選ぶようになりました。
しかし、その裏には「ステマ(ステルスマーケティング)」や「サクラ」と呼ばれる不正な宣伝手法が潜んでいることがあります。
どちらも消費者を惑わせる行為ですが、意味や手法には明確な違いがあります。
この記事では、それぞれの意味や特徴、問題点などを解説します。
ステルスマーケティング(ステマ)とは?
ステマについては、以下の記事をご参照ください。
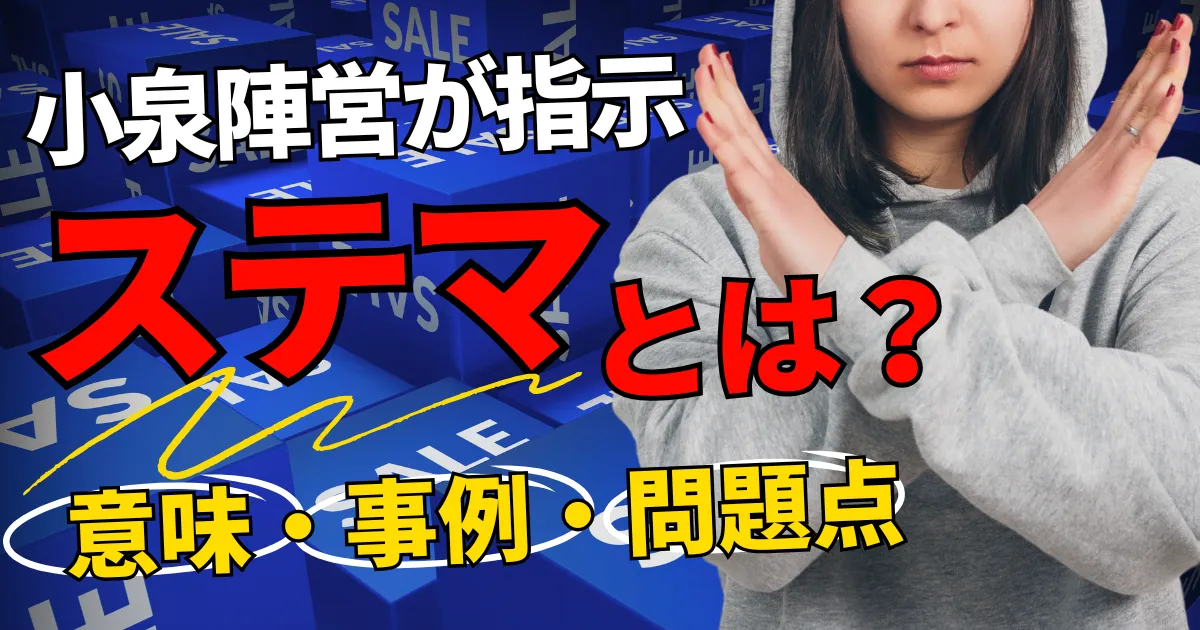
サクラとは?
サクラは日本で古くから使われてきた言葉で、現代ではネットや店舗など幅広い場面で問題視されています。
サクラとは、実際の客や利用者を装って商品やサービスを褒めたり、人気があるように見せかけたりする行為を指します。
もともとは芝居小屋や寄席で、雇われた人が観客のふりをして盛り上げることから生まれた言葉です。
以下のような例があげられます。
- 飲食店のレビュー操作
一部の飲食店がアルバイトを雇い、グルメサイトに虚偽の高評価レビューを投稿する。 - ネット通販でのサクラレビュー
海外製品を中心に、購入していない人が高評価レビューを大量に投稿する。 - イベントやセミナーでの動員サクラ
実際には参加者が少ないのに、サクラを入れて「満席」と演出する。
サクラは「その場にいる人」や「レビューを読む人」を直接的にだます点が特徴で、消費者の判断を誤らせる大きな要因となります。
ステマとサクラの違い
ステマとサクラは似ているようで異なる手法です。違いを整理すると以下のようになります。
| 項目 | ステマ | サクラ |
|---|---|---|
| 定義 | 広告であることを隠して宣伝する行為 | 消費者のふりをして商品の売れ行きやイベントの雰囲気などを偽装する行為 |
| 主な場面 | SNS、ブログ、YouTube、口コミサイト | 店舗、イベント会場、レビュー欄 |
| 規模 | ネットを通じて不特定多数に影響 | その場にいる人やレビューを読む人に影響 |
| 主な規制 | 景品表示法で明確に規制、消費者庁から「措置命令」が出され、改善を求められる。 | 景品表示法に抵触する可能性 |
| 罰則 | 措置命令に従わない場合、2年以下の懲役又はは300万円以下の罰金(法人は最大3億円の罰金)に処される可能性があり | 詐欺罪などで処罰される場合あり |
| 罰則の対象 | 広告主(企業・事業者) | サクラを雇った事業者や関与した個人 |
景品表示法のルール
景品表示法の第5条で以下を不当な表示として禁止しています。
①優良誤認
②有利誤認
③①と②に掲げる他に一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
引用:e-GOV法令検索
優良誤認表示の例
商品やサービスの品質・性能などについて、実際よりも著しく優れていると誤認させる優良誤認表示の例は以下のようなものがあります。
- 「天然鉱石」を使用した装飾品と表示して人造鉱石を使用。
- 「国産ブランド牛」と表示して輸入牛を販売。
- 「100%天然成分」と表示して一部に合成成分を使用。
有利誤認表示の例
価格や取引条件について実際よりも有利だと誤認させる有利誤認表示の例は以下のようなものがあります。
- 「通常価格1万円 → 今だけ5千円!」と表示しながら、実際には常に5千円で販売している。
- 「送料無料」と表示して実際には手数料を上乗せ。
- 「業界最安値」と宣伝しながら、他社より高い価格設定。
サクラを見分けるポイント
サクラは巧妙に仕込まれているため、完全に見抜くのは難しいですが、以下のような特徴を知っておくことで「怪しいレビュー」や「不自然な盛り上がり」に気づけるようになります。
- レビュー内容が極端に偏っている
→ 「最高!」「絶対おすすめ!」など、根拠のない絶賛が並んでいる場合は要注意。逆に低評価がほとんどないのも不自然です。 - 同じような文章が繰り返されている
→ 複数のレビューで似た言い回しや同じ表現が使われている場合、サクラの可能性があります。 - 投稿者のプロフィールが不自然
→ レビュー数が極端に少ない、または短期間に大量のレビューを投稿しているアカウントは怪しい傾向があります。 - タイミングが集中している
→ 短期間に高評価レビューが一気に増えている場合、組織的にサクラが動いている可能性があります。 - 現実離れした体験談
→ 「芸能人も使っているらしい」「人生が変わった」など、過剰にドラマチックな体験談は疑ってかかるべきです。
まとめ
ステマとサクラはどちらも消費者をだます宣伝手法ですが、ステマは「広告であることを隠す行為」、サクラは「客や利用者を装う行為」という違いがあります。
どちらも発覚すれば企業やサービスの信頼を大きく損なうため、今後は規制も強化されていくでしょう。
私たち消費者も、情報を見極める目を持ち、冷静に判断することが大切です。